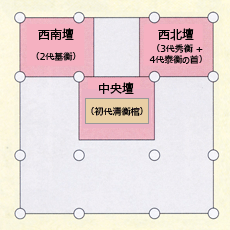コスモロジーと出会うよろこび【編集部から】
本連載エッセイでは、人類共通の記憶の宝庫ともいうべきコスモロジー(=世界観・宇宙観)の豊かさを武澤秀一先生が探究します。
建築家である先生は、ご著書『空海 塔のコスモロジー』『マンダラの謎を解く』『神社霊場ルーツをめぐる』に見られるように、3次元の存在である建築を歴史・宗教・文化の位相のなかに捉え、塔やマンダラや神社霊場が聖なる力を帯びていく様相を明らかにされてきました。そして今年3月に刊行された新著『伊勢神宮の謎を解く』は、とくに日本の特性を浮かび上がらせていて注目されます。本連載エッセイにあわせて、ぜひごらんください。これからの連載でも、日本列島において育まれてきたわたしたちのこころの特性に、さまざまな場面で気づかせてくれることでしょう。
さあ、コスモロジーに出会う旅に出発することにいたしましょう。わたしたちが無意識の底に置き去りにしてきた大切なものに、今、再び出会うために——。
建築家 武澤秀一の連載エッセイ 時空を超えて コスモロジーと出会う
第19回 北の仏国土 (中)
|
〈金色堂の今と昔〉平安末期の1189年、源頼朝は平泉を陥落させ、奥州藤原氏を滅亡に追いやりました。その頼朝に寺僧が提出した文書「寺塔已下注文」に、中尊寺金色堂はつぎのように記されています。 上下四壁、内殿は皆金色なり。堂内に三壇を構ふ。悉く螺鈿(らでん)なり。阿弥陀三尊、二天、六地蔵、定朝(じょうちょう)これを造る。
「上下四壁」とは、天井・床・4周壁のこと。つまり堂内すべてが金色であるといっています。そこには三つの須弥壇(しゅみだん)があり、ことごとく螺鈿細工で飾られている。 |
〈遺体が眠る霊廟だった〉
|
〈棺の寸法が決めた金色堂の規模〉
このことを裏付けるのが、金色堂の小ささです。間口・奥行ともに、1.6メートル-2.2メートル-1.6メートルの柱間からなり、全体として5.5メートル×5.5メートルの正方形をなしています(床面積は30平方メートルに過ぎません)。そして扉の高さは1.5メートル弱で、頭がつかえてしまいます。大勢のひとが出入りすることは想定していない造りです。 |
〈極小世界だから実現できた〉
金色堂がなによりもまず霊廟として建てられたとして、それでは、なぜ、これほどまでに小さくする必要があったのか? |
〈金色堂と平泉館の関係〉
阿弥陀仏の極楽浄土は西方にあり、したがって多くの場合、阿弥陀堂は西を背にして東面します。つまり、ひとは西に向いて拝むことになります。 一 館の事〈秀衡〉 平泉館と呼ばれる秀衡の宿館は金色堂の「正方」、つまり真向かい建てられていたのです【図H-3】。平泉館は金色堂からかなり離れた平地にありますが、山上の金色堂と平地の平泉館は対面し合う関係にありました。平泉館から正面に関山を仰ぎ、山上に煌めく金色堂を拝していたのです。 
【図H-3】:中尊寺金色堂と平泉館の関係図。阿弥陀堂でもある金色堂は真東にむくのが本来のありかただが、やや南に振れて東南東にむき、平泉館と正対する関係にあった
この関係がいつからなのかが、つぎの問題となります。 |
〈宙に浮く「中尊寺供養願文」〉
さきに「中尊寺供養願文」を引きましたが、これは国の重要文化財に指定された有名な文書です。しかし、この文書をめぐって、じつは大きな論争が巻き起こっているのです。 ・三間四面檜皮葺堂 一宇 左右廊二十二間あり
この記載内容は現状と合わないだけでなく(金色堂に関する記述もない)、当時の伽藍の状況をもっとも精確に伝えているはずの「寺塔已下注文」とも合わないのです。
こうなりますと、「中尊寺供養願文」そのものの信憑性に疑問が出てきます。五味氏は、この願文は「清衡を願主に想定して後世に作られた」としています。中尊寺が鎮護国家の大伽藍として復興されることをもとめて、この願文が作られたというのです。 「願文」は後世、つまり南北朝期の1336年ないし1337年に書写されたとみられますが、この時に、これから造りたい伽藍の概要が「願文」として書かれた疑いがあります。 1337年3月に中尊寺は金色堂と経蔵を除き、ほとんどの堂塔を焼失しています。この事態を受けて、「願文」が新たに起草されたのではないか。書写されたのではなく――。 (この場合、「願文」が新たに起草されたのは火災が起きた1337年3月以後ということになる) このように立派な大伽藍がかつて存在したのに、今はない。これを「復興」することを是非とも許可し、援助してほしい――。多くの堂塔を焼失した今、書写を装って、じつは起草した「供養願文」を復興の根拠とし、新たな大伽藍建立のための芝居を打ったのではなかったか。 つまり「大伽藍一区」とは、焼失してしまった中尊寺の多くの堂塔が存在していた「一区」なのであり、そこに新たに造営したい建物を書き連ねたのが、ほかならぬ「中尊寺供養願文」だったわけです。 そういえば、「三間四面檜皮葺堂 一宇 左右廊二十二間あり」とか、「二階瓦葺経蔵 一宇」とか、「供養願文」にしてはやたらと具体的で、あたかも「工事計画書」のような感があります。 すでに落成した伽藍を供養する「願文」なら、「三間四面檜皮葺堂 一宇 左右廊二十二間あり」は「釈迦堂 一宇」、「二階瓦葺経蔵 一宇」はたんに「経蔵 一宇」でいいように思われます。必要にして十分な援助が得られるよう、建物の規模や仕上げを具体的に訴えることが目論まれたのではないか。 実際にはこれは実現されませんでした。現在までにおこなわれた発掘調査の結果は「寺塔已下注文」に記載された内容に近く、「中尊寺供養願文」に記載された伽藍に相当するものは皆無に等しいと報告されています。
|
〈「中尊寺供養願文」のこころは永遠に〉
しかしそうなると、「願文」における、前回紹介した清衡の感動的なことばはどうなってしまうのでしょう。それは上記の「二階鐘楼 一宇」の鐘の音に託して述べられたことばなのでした。 |
(つづく)
註記:図版出典および参考文献は、第20回「北の仏国土(下)」において纏めて掲げます。
 |
武澤 秀一(たけざわしゅういち) 1947年群馬県生まれ。建築家/博士(工学・東京大学)。東京大学工学部建築学科卒業。同大学院を中退し、同大学助手をへて建築家として独立。設計活動の傍ら、東京大学、法政大学などで設計教育指導に当たった。20代、30代はヨーロッパ志向がつよかったが、40代に入りインド行脚をはじめる。50代以降は中国、韓国および日本列島各地のフィールドワークを重ねている。著者に、『マンダラの謎を解く』(講談社現代新書)、『空海 塔のコスモロジー』(春秋社)、『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)、『神社霊場 ルーツをめぐる』(光文社新書)、『伊勢神宮の謎を解く——アマテラスと天皇の「発明」』(ちくま新書)などがある。 |