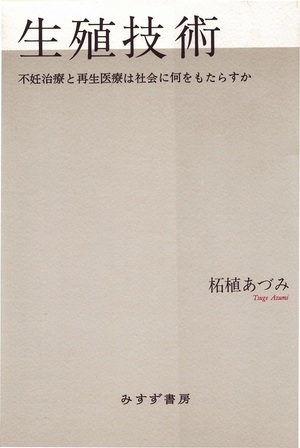- トップ
- 宗教情報PickUp
- 『生殖技術』
| 文字サイズ: | 大 | 標準 | 小 |
書評
日本国内で刊行された宗教関連書籍のレビューです。
約一ヶ月、さまざまな分野の書籍からピックアップしてご紹介します。毎月25日頃に更新します。
興味深い本を見逃さないよう、ぜひとも、毎月チェックしてみてください。
メールでの更新通知を希望される方は、letter@circam.jpまでご連絡ください。
最新の書評 2012/11/03
『生殖技術』 柘植あづみ(著)みすず書房 2012年9月 3200円(税別)
生殖補助技術の発達は、精子や卵子の商品化、人体の資源化、親子や家族とは何かといった問題を提起してきた。著者は、これらの問題について、新聞記事の表現や語彙に潜む思想など些細な点をも見落とさずに拾いあげて切り込んでいく。明治学院大学教授であるとともに、不妊の人たちへのサポートグループ「フィンレージの会」の設立と運営に携わった著者だけあって、患者の感覚と齟齬を生じている医療研究者や国際競争のため研究を推進する国家に批判的なスタンスでは一貫している。
「不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか」とのサブタイトル通り、人々の意識や社会のあり方を考察していくので、先端医療技術に疎い人間でも、巻末につけられた用語解説を見ずに読み進められる。他人に提供する卵子は営利目的でなく無償提供ならば良いのか? インフォームド・コンセント(情報提供の上の同意)に基づく卵子提供は、本当に自発的なのか? 代理母には利他的精神が強調されるが、そこに問題はないのか? iPS細胞には本当に倫理的な問題はないのか? など。そして、生殖医療が米国からインドなどへと移っている背景、代理出産に関わる費用の受け取りに見られる矛盾、政府の規制の問題点などを容赦なく突く。問題の炙り出しが巧みで、考えさせられる点が多々あり、密度の濃い演習にでも出席したような読後感だ。個人的には、iPS細胞(人工多能性幹細胞)の研究によって山中伸弥・京都大学教授のノーベル医学生理学賞受賞が決まったことは喜ばしいが、受精卵を壊さないとはいえiPS細胞の研究に問題がないとは言えないだろうと思っていたので、我が意を得たり、との感もあった。
問題提起に沿って、病気や障碍は治すべきものなのか、医療技術が不妊で苦しむ人たちを癒せるのか、医療によって子供ができれば「幸福」なのか、等々と考えていくと、病気や不妊といった問題は社会的な問題であり、社会的な解決が必要であるとの指摘が腑に落ちる。生殖技術が発達する一方で、「心の悩み」を解決し、偏った社会意識に一石を投じる働きが機能していなかったのかもしれない。ここは、宗教者を含めた文系人間の活躍が期待されるところではないだろうか。議論すべき素材がぎっしりと詰まった読み応えのある1冊だ。
※この書籍は、レポート「出生前診断と宗教」の執筆に際して、参考文献としたものである。
藤山みどり執筆レポート「出生前診断と宗教」はこちら
※この書籍は、レポート「出生前診断と宗教」の執筆に際して、参考文献としたものである。
藤山みどり執筆レポート「出生前診断と宗教」はこちら
(宗教情報センター研究員 藤山みどり)