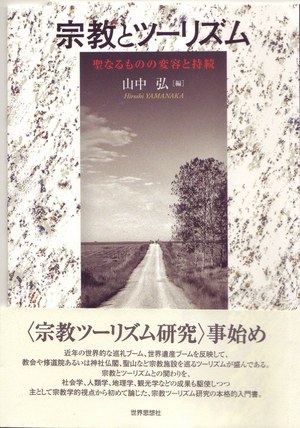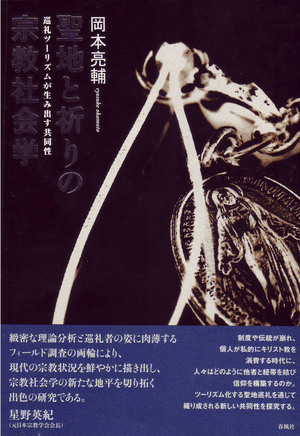- トップ
- 宗教情報PickUp
- 現代における聖地の意味を問う二冊――宗教、巡礼、ツーリズム――
| 文字サイズ: | 大 | 標準 | 小 |
書評
日本国内で刊行された宗教関連書籍のレビューです。
約一ヶ月、さまざまな分野の書籍からピックアップしてご紹介します。毎月25日頃に更新します。
興味深い本を見逃さないよう、ぜひとも、毎月チェックしてみてください。
メールでの更新通知を希望される方は、letter@circam.jpまでご連絡ください。
最新の書評 2012/09/27
現代における聖地の意味を問う二冊――宗教、巡礼、ツーリズム――
『宗教とツーリズム――聖なるものの変容と持続』 山中弘(編著) 世界思想社 2012年7月 2100円(税別)
『聖地と祈りの宗教社会学――巡礼ツーリズムが生み出す共同性』 岡本亮輔(著) 春風社 2012年5月 5000円(税別)
近ごろ「パワー・スポット」や「聖地巡礼」といったことばを耳にする機会が増えた。テレビのワイドショーや旅行雑誌を中心とした各種媒体で特集が組まれるなど、日本全国にある宗教的場所――狭義の「聖地」に収まらない――が注目されている。お伊勢参りや修験道、山岳信仰にまつわる風習が地域によっては根強く残っているように、日本ではがんらい神社仏閣が物見遊山の対象となる宗教文化はあった。「宗教的場所に人々が集う現象」に焦点を当てることは、しばしば「曖昧」とされてきた日本人の宗教性について、具体的に捉えようとする試みともいえる。これらは古典的な宗教学(宗教学者エリアーデの「聖俗論」などにおける、宇宙の中心としての聖なる場所(大樹や柱などがその印となる)を想起させるけれども、現代の聖地においては、宇宙の中心は(そこにあるだけでなく)構築され、演出される。その複雑な力学を捉えようとしたのが、これから紹介する二書である。いずれも、筑波大学を拠点にした、宗教とツーリズムの研究会およびそのメンバーが生み出したものである。(1)世俗化社会、(2)日本的宗教性、(3)場所と宗教性、この三者を多面的に捉えるよすがとして、以下で検討していきたい。
◇宗教とツーリズムとの接合
筑波大学・山中弘氏の編著『宗教とツーリズム――聖なるものの変容と持続』[世界思想社、07/2012]は、冒頭で「一九八〇年代半ば以降、ツーリズムは世界最大の産業になったといわれている」(p.3)として、国内外への旅行者の増加とその産業規模の拡大について概観し、さらにツーリズムの影響が宗教の領域にも深く浸透していると強調している。
ツーリズムと宗教との具体的な関係性については、本書の各章にて展開される各地域の事例を追っていくことで、確認することができよう。たとえば、對馬論文(第1章)は、「聖地」へのアクセス手段としての鉄道がどのように相乗的に参詣者を増やして「聖地」をもり立ててきたかをつまびらかにする。神仏分離と江ノ島の神社(森論文、第2章)、伊勢神宮をプロモーションする地元の取り組み(板井論文、第3章)、「癒し」の聖地ルルドの雰囲気を作るのは「傷病」者であるという事実(寺戸論文、第4章)、カトリックの「聖地」、サンティアゴ・デ・コンポステーラが、信仰なき巡礼者の期待が投影されて構築されているという指摘(岡本論文、第5章)など、具体的な事例とデータに基づいて、「聖地」を作る仕組みが単純な「聖」性ではないことが暴かれていく。第6章の浅川論文では、近年、四国遍路が巡礼路としての人気を集めていることに着目し、それらについて社会における遍路ブーム、マス・メディアによる一般への普及、そして遍路巡礼者を受け入れる側の地域のとりくみ、について紹介している。巡礼に訪れる人々に対するホスト地域の住民による「お接待」というもてなしは「遍路道再生運動」として捉え直される。
本書は「宗教とツーリズム」、「巡礼とツーリズム」、そして「世界遺産とツーリズム」と、さまざまな事例を吟味する。編者の山中氏があとがきに記したように、「聖地」の「聖性」とは、近代的なまなざしを経て新たに構築されたものではないか、来訪者の期待を投影したものではないかと問うのである。ただし、宗教はツーリズムに従属する変数といえてしまうであろうか、このことは、本書を経て、改めて問われるべきことであろう。
◇世俗化社会における聖地巡礼
ツーリズムという視点から世俗化社会における人々の多様な宗教性に迫ろうとした研究が先の論集(『宗教とツーリズム』)であったとすれば、岡本亮輔氏の著書『聖地と祈りの宗教社会学――巡礼ツーリズムが生み出す共同性』[春風社、05/2012]は、人々が宗教的場所へと足を向ける現象について、世俗化社会、さらにはポスト世俗化社会における個々人と宗教との関係性に焦点を当てた議論である。
本書は二部構成である。
第Ⅰ部は、高度に近代化の進んだ世界において、宗教と社会と個人との関係がどのようであるか、主として宗教社会学関連領域における多くの議論のレビューである。この分野になじんでいれば、たいへんエキサイティングな内容であるのだが、このサイトの読者にとっては専門的すぎる概念におぼれてしまい、よりおもしろい第二部に至る前に挫折してしまうだろう。そこで第Ⅰ部について、ここでは岡本の論点および結論を確かめるだけにしたい。まず膨大な数の先行研究レビューに充てられた第Ⅰ部の議論は、近代の宗教論の中核となる宗教の「私事化」という概念――宗教は自律的個人がばらばらに私的に行う細分化された行為となる近代において、教会での礼拝などの宗教的共同行為は力を失う、が、私的な行為としては以前よりも力を持つといえるかもしれない――を検証し、さらにポスト近代のあり方を検討する点にある。そして先に岡本の結論を述べるならば、世俗化において私秘的性格を強めた宗教は、ポスト世俗化において再び個人の次元を越えた共同性を目指す、というものである。
第Ⅱ部においては、ポスト世俗化の巡礼ツーリズムの具体的な事例が挙げられる。奇跡のメダル教会、サンティアゴ巡礼、テゼ共同体、「聖地」巡礼プログラムを提供する「新共同体」の四つが取り上げられる。いずれにおいても重要なのは、巡礼者あるいはツーリストたちの「横」のつながり、巡礼における「真正性」つまり本物であることの理解の多様さである。「本物」の巡礼は、一つではないのである。この第Ⅱ部は、第Ⅰ部の宗教社会学的議論に通じていなくても、四種の事例を味わうことができる。第Ⅱ部を先に読んで、四種の事例を踏まえて第Ⅰ部を考える、という読み方も可能であろう。
第Ⅱ部においては、ポスト世俗化の巡礼ツーリズムの具体的な事例が挙げられる。奇跡のメダル教会、サンティアゴ巡礼、テゼ共同体、「聖地」巡礼プログラムを提供する「新共同体」の四つが取り上げられる。いずれにおいても重要なのは、巡礼者あるいはツーリストたちの「横」のつながり、巡礼における「真正性」つまり本物であることの理解の多様さである。 「本物」の巡礼は、一つではないのである。この第Ⅱ部は、第Ⅰ部の宗教社会学的議論に通じていなくても、四種の事例を味わうことができる。第Ⅱ部を先に読んで、四種の事例を踏まえて第Ⅰ部を考える、という読み方も可能であろう。
新共同体とは、「聖地」の訪問や大集会をツアーパッケージとして提供する主体である。さまざまなメディアで提供されるツアーパッケージのなかには、一度忘れられた聖地を復興させるような運動も含まれる。
宗教を紐帯としてとらえたJ.P.ヴィレムの定義を踏まえる岡本は、複数の領域で私事化が進む後期近代であるからこそ、自律性を備えた諸個人が結びつくことが必要になり、他者に対して自らを開示するような関与の仕方が求められ、そのために宗教資源が流用される。上述した巡礼・ツーリズムはいずれもそのような関与の仕方を提供する宗教資源であるのだと示すのである。または、第Ⅱ部で紹介された事例こそが、岡本にとっては第Ⅰ部で述べたこと、つまりポスト世俗化社会における個々人と宗教と関係性が、現実的に描かれる場所と捉えることもできるであろう。
本書は、8頁にわたるカラーの口絵に加え、本文中に数多くの写真を納めて、読者を巡礼の道へと誘う。そのために、第二部は第一部に比べて読者の足取りは軽くなるはずである。
最後に一言付け加えておくと、携帯ストラップをマクロで取った印象的なカバーを外すと、本の装丁は巡礼の『集印帳credential』となっている。著者と編集者は、旅情をかき立てられるこの本を楽しみながら作ったに違いない。
*なお『聖地と祈りの宗教社会』の著者である岡本亮輔氏に寄稿頂いた当サイト・コラム(第2回)「自分探しの聖地、何もない聖地」も是非ご覧下さい。
(蔵人)