- トップ
- 宗教情報PickUp
- 書評
- 書評 バックナンバー一覧
- 『墓と葬送のゆくえ』
| 文字サイズ: | 大 | 標準 | 小 |
宗教情報PickUp
書評 バックナンバー
2015/05/08
『墓と葬送のゆくえ』 森謙二 著 吉川弘文館
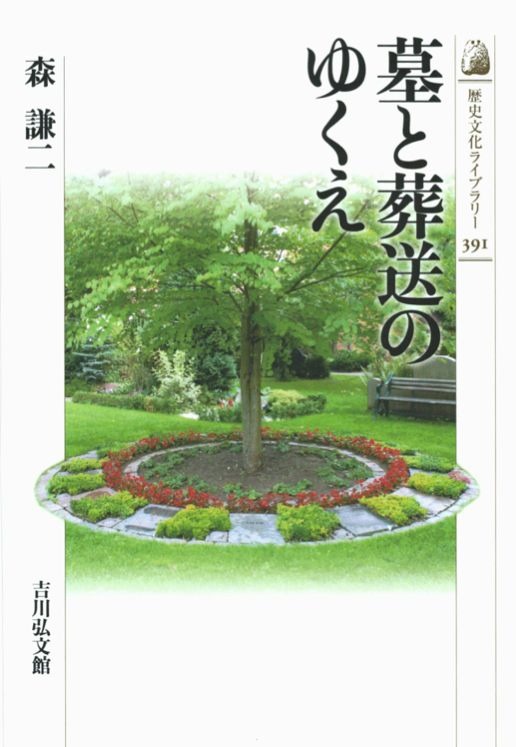 |
| 2014年12月 1836円 |
■はじめに
現代日本の葬送慣行の動向を考える際、1991年10月5日に「葬送の自由をすすめる会(以下、「すすめる会」)」(安田睦彦会長・当時)が行なった散骨は、ひとつの出発点になる。同会による散骨は三浦半島沖で行なわれた。参列者らは、焼骨して砕いた遺灰を花と一緒にヨットの上から海へと流した。遺骨遺棄罪にあたる可能性のある散骨について、法務省刑事局はすぐに「刑法190条の規定は社会習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的であり、葬送のための祭祀で節度をもって行なわれる限り問題ない」との公式見解を出した。
朝日新聞は1991年10月16日付・朝刊で、「「散骨」認めます 法務省が見解「節度あれば」」との見出しで、「すすめる会」の散骨の実施を伝えている。それから、約24年が過ぎた。現在、同会会長をつとめる島田裕己は、『0ゼロ葬』(集英社)、『葬式は、要らない』(幻冬舎)などを著している宗教学者。「葬送の自由」は今日も、様々なかたちで模索され、すすめられていると言ってよいだろう。
本書のプロローグも、1990年代初頭の新しい葬送の展開を概観するところから始まる。森は、伝統的な墓のあり方に漂う閉塞感として、次の3つを挙げる。(1)墓地用地の確保が困難になるほどの土地の高騰、(2)家族(アトツギ)による墓の継承慣行の揺らぎ、(3)婚家の墓に入りたくない女性(妻)たちの増加(p.4-5)。また、法務省の見解によって、「日本人の葬送=「埋葬」に関するコンセンサス(同意)が崩れ、新しいルールをつくれないまま古いルールが壊された」(p.6)とも述べている。さらに、埋葬されずに遺体を放置する事件や、葬式をあげない人たちの増加などから、「「生の世界」から「死の世界」に移行するときに、一定の儀礼を通過することは人間の普遍的な「常識」であった。その常識がいま崩れようとしている」(p.8)と述べ、祖先祭祀に代わる新しい社会常識・社会規範の模索が続いているのが現況だと分析する。
森は、社会学者のアーウィン・ゴッフマンに言及しながら、社会関係を構築・維持する相互行為として儀礼を捉え、「儀礼を失ったときに私たちは人間関係そのものを失うことになる。これが私の「答え」の一つである」(p.9)と、自らの立場を提示している。加えて、「人は埋葬される権利を持つ」とし、基本的人権の範囲内にこの「埋葬される権利」を含めて考えるべきで、その上で、「散骨」が埋葬の方法として妥当であるかを検証すべきだと述べている(p.9)。以上のことをまず確認し、本書の内容を追ってみよう。
■「法務省見解」が壊した埋葬のルール
現代日本の葬送文化の特質と課題について、本書の中では何点もの指摘があるが、その中でも重要な指摘は、これまでに埋葬がどのように維持されてきたかという点についての分析である。
日本の埋葬は、次の3つのトライアングルによって保たれてきたという。その3つとは、①祖先祭祀の観念、②刑法(死体遺棄を含む刑法第24章の5か条)、③墓地埋葬法である(pp.51-58)。このトライアングルを、「はじめに」で指摘のあった墓にまつわる閉塞感に照らして整理してみよう。まず、土地高騰によって墓地用地確保が困難になる現況は、①と③に関わる。家族は核家族化し、ひとは個人化して、それまで当たり前に行なわれていた「そうであるべき」常識的な葬送慣行を続けることが難しくなる。アトツギ問題も、この①と③に関わることである。婚家の墓を拒否する女性たちの増加も、①と③にかかわる現象だ。
②の刑法は、閉塞感の形成には表立って影響していないように見える。しかし人類史上、死者の扱いを最も厳格に規定してきたのが、じつはこうした法と規範である。その意味で、日本社会において、「散骨」は法的に問題なしとの判断が広がれば、そこを突破口として埋葬法が多様に展開すること(=散骨、樹木葬、宇宙葬等々)は、必然だと思われる。そして、法的に規制されてきた個人の「葬送の自由」が、「自己決定」や「死者の意思の尊重」の名のもとに、一つの権利となる。
1990年の「法務省見解」の問題点を、本書は次の4つにまとめている。①「散骨」と遺骨の「遺棄」の線引きが曖昧。②骨を撒きたい都市住民と撒かれる土地に住む農村・山村・漁村の人々との対立。③「葬送の自由」は個々人の自己決定だけに関わることではなく、葬る手続きは多数の人々の社会的合意を必要とするという点。④現行の墓地埋葬法では、埋葬施設の設置・使用には都道府県や市町村の許可が必要だが、散骨される場に許可が必要ないというのは、法的な整合性を欠く。
こうした問題点があるにもかかわらず、「葬送の自由」が野放しになっている現状。本書は、まずこの点を再考している。そして、「人を葬る」とはどういったことなのかといった、より本質的な問いへと進む。事例として紹介されている葬送文化の範囲は、日本のみならず、ニュージーランド、イタリア、ドイツなど世界各地に及ぶ。こうした広い目配りも本書の魅力のひとつだ。葬送文化のみならず、ローカルな文化と社会がグローバル世界の仕組みの一部を構成し、その中で再帰的に変容していく様相は、多くの領域にみられるが、本書では「市場化」という原理を軸にして、日本の葬送の変遷を「第一の近代化」、「第二の近代化」という区分で整理している。これを追ってみよう。
■葬送の市場化 — 二つの近代化
本書が指摘する葬送の段階的変遷、それを貫く原理は「市場化」である。現代は、いわば業者への丸投げにまで極まった葬送だが、ここまでにはいくつかの段階があるというのが、本書での整理である。
日本における火葬の受容は、8世紀まで遡るという。天皇や皇族を中心とする上層階層の一部が火葬をはじめ、平安時代末期から鎌倉時代には広く上層階層に火葬が受容され、「火葬後に残された焼骨を骨壺に入れ、それを仏教寺院に納骨したり、あるいは遺骨を墳墓に入れるという習俗」が形成されていったという(p.91)。明治以降、火葬は急速に一般の人々の間に浸透していく。1990年に29.2%だった火葬率は、1925年には43.2%に上昇。その理由は、「遺骨を保存するという日本独自の方法をすでに発見していたために、祖先祭祀の思想が浸透していく近代日本においても火葬を受容することができた」(p.95)からだという。
土葬が主だった時期には、地域共同体の人員は「墓穴堀り」の働き手として葬送にかかわり、遺体を墓地へと運ぶ葬列をなした。しかし火葬の広がりによって、地域共同体のメンバーらは葬儀から次第に手を引いていく。1919年(大正9年)には、東京都で「東京葬祭具営業組合」が発足し、葬送の「市場化」が進むことになったという。「葬列が廃止されることによって、自宅であれ斎場であれまたは寺院であったとしても。葬儀の儀礼の場が<告別式場>になっていく」(p.106)。これが、高度経済成長期に多様化し、贅沢なものになっていく。
ここでの要点は、葬儀の場で地域の人々が請負っていた役割を葬儀業者のサービスが代替するようになったことである。葬儀の役割を、本書は次の5つに整理している。①死を世間(社会)に知らせること、②死者と生者を分離すること、③死者をあの世に導き安定させること、④死の穢れの拡散を防ぐこと、⑤生者の世界を再構築すること(p.107)。葬送の市場化は、これらの役割にはほとんど配慮しない。そして「喪家と葬儀業者によって作り出された「悲しみ」の舞台だけが用意されることになった」(p.108)という。
さらに、「葬儀の参列者の変化」という指摘も重要だ。地域社会とのつながりの薄い人が亡くなっても、その葬儀に参列するのは死者の仕事・職場関係の知人や、家族・親族に限られるようになる。個々人が地域社会への依存度を低めるようになると、死と葬送という側面でも個々人は地域社会と関わることなく、葬祭業者のサービスを商品として購入・消費し、葬送を行なえるようになった。これを本書では、葬送の「第一の近代化」と呼んでいる(p.109)。
この「第一の近代化」に続き、本書が指摘するのは、葬送の「第二の近代化」である。これは、家族さえも葬送領域から手を引き、業者にそれらを委ねていく動きのことだという。つまり、核家族化によって、祖先祭祀供養を引き受けられない家族が増え、アトツギによる継承を前提としない新しい葬法が模索され、「自己決定」の名のもとに、「葬送の自由」が主張され、近年では「埋葬されない死者」さえ出てきている情況を指している(pp.124-142)。
本書の指摘のように、「自己決定」の尊重によって葬送の仕方に変化が生じてきている。これは確かだ。ここで、本書の根本的な問いが出されてくる。葬送における「自己決定」論では、死後の安寧を求めることは難しいのではないか、と。この点を考える際の重要概念は、「依存」である。
出生は子供の自己決定に基づくものではないし、幼少期においては誰か(一般的には両親)に依存しなければ生きていくことはできない。と同時に、人生の最後の段階でも「他者」への依存を必要としている。高齢になって身体が衰えてきたときには、誰かに介護をお願いしなければならないし、何よりも死後、自己を墓地(火葬場)まで運んでくれる「他者」を必要とする。ここに「祖先祭祀」に代わる死者のケアーについての新しい倫理を必要としていることがわかる。(p.142)
すでに、家族・親族・知人らとの関係が薄くなり、「他者の不在」「他者の拒絶」が進み、葬送の現場においても「他者との関わりを拒絶することで死者と他者の人間関係が存在しなかったかのようにふるまう」(p.143)という現況がある。これまでは、自宅死から病院での死の増加に伴い、死、死者が不可視なものになるという現象は、「死の隠蔽」として語られてきた。それよりも更に、積極的に社会から死を隠す事態が進みつつある。それを本書は「他者の拒絶」と呼ぶ(pp.144-150)。
家族葬や直葬が増える現場で語られる「他人に迷惑をかけたくない」という思考は、じつは「他者との関係を持ちたくないという考えの裏返しでもある」(p.154)と、本書は指摘する。これは、親密な人間関係としての家族どうしにも当てはまる。「家族に迷惑をかけたくない」という思いが、じつは家族の共同性を解体する。そして、「この解体現象の背景にあるのも、家族領域への市場原理の導入である」(p.155)というわけだ。
■死者の尊厳を守り、埋葬の脱商品化を
葬送の目的を「死者を共同体に位置付けること」と述べたヘーゲルを引用しつつ、本書は、死者の尊厳を守ることは、「死者を「埋葬」することであり、死者と社会との繋がりを記憶し死者の安らぎをまもること」(p.161)だと主張する。そして「葬送の自由」の議論には、「死者の尊厳性」「死者への敬意」にどのように配慮するかという視点が欠けていると指摘している(p.163)。
そして、こうした死者の尊厳を守るという視点からすれば、新しい葬法にはいくつかの問題点が含まれているという。例えば、急速に展開する「合葬式共同墓」。これは、「不特定多数の他人の焼骨を預かり共同で焼骨を埋蔵あるいは収蔵する施設あるいは埋蔵地(墓地)」(p.168)のことだが、一般には「永代供養墓」として知られている。しかし、この語では「誰が永代にわたって供養するのか」、寺院なのか、契約・利用者なのかが曖昧であるという。また、「合葬」「共同」の意味にも、疑問が残るという。つまり、このお墓は使用権を得れば不特定多数の誰でも入ることが出来る墓であり、それは「見方を変えるとすれば、それは無縁墳墓になった無縁の遺骨の集合体である無縁塔とどこが違うのか」(p.165)ということになるからである。
供養の「時間」という観点からの疑問もあるという。これまでは、「家族や親族の人々が時間をかけて死者を「個」として慰霊するところに「供養」の意味があったのであり、新しい葬法ではこの時間が消えてしまった」(p.173)と。樹木葬についても、「人間の遺骨を死後すぐに自然の循環におくことが「埋葬」といえるのか」(p.177)という疑問が残るという。
本書で繰り返されるこうした疑問の底流には、死者にとっての「他者」としての生者と、生者にとっての「他者」としての死者との関係を、包括的に捉えにくくなっている現代社会の状況がある。
また、葬送が市場原理に委ねられることで、「死者の属した環境や所得(資産)に応じて「埋葬」のあり方が大きく異なってくる」(p.198)。その際に生じる問題として、本書は次の3つを指摘している。①死者に親密な人間関係がなければ、遺体は放置され、孤独死・無縁死が増える。②アトツギの居ない人々は、非承継型の新しい葬法を選ばざるをえない。③アトツギがいる人も将来には無縁墓として改葬される可能性がつきまとう(pp.198-199)。
結論として本書は、「日本近代の伝統的な「埋葬」のシステムを問い直し、新たな秩序を再構築すること」(p.199)が必要だと説く。そして、G.エスピン・アンデルセンの用語を引用しつつ、<「埋葬」の脱商品化>というアイデアを提示している。「誰もが「埋葬」される権利を社会=国家が保障すべき」(p.199)だと。墓地行政を市町村が責任をもって提供する福祉サービスのひとつとして位置付けることで、「埋葬」の脱市場化・脱商品化を目指す。これが、本書が示す具体的ビジョンである。
■「終活」よりまず福祉
現代の葬送文化を研究する第一生命経済研究所主席研究員・小谷みどりは、生前に葬儀の準備をする昨今の「終活」ブームが、高齢化・多死社会の不安に乗じて仕掛けられたものであると指摘している。そして、マスコミが「死」を「終活」と言い換えたことでネガティブなイメージが消え、現在の多死社会が「終活」ビジネスの大きなマーケットになってきたと分析している(「仕掛けられた就活ブーム」『中央公論』2014年10月号)。
社会の無縁化によって、葬儀も墓も消費の対象としてのサービスや財となる。「終活」という用語は、「死の隠蔽」「他者(=死者)の拒絶」に、一役もふた役も買っているものとして理解できよう。次々と出てくる「新商品」を消費するか、死が共同体の出来事として意味づけられてきた歴史に立ち返りつつ、新たに「福祉」の枠組みで葬送を再考・再構築するか。制度が整えられるには、議論と時間を要するだろう。
人間は、究極的には独りで死にゆく存在である。しかし一方で、社会的存在として生きているという点も、疑いのない事実である。万人が安心して死んでゆける社会を目指す。これは、今生きているひとりひとりの人間が行なう生前の実践としては、「終活」よりも大きな意義があろう。
(宗教情報センター研究員 佐藤壮広)
