- トップ
- 宗教情報PickUp
- 書評
- 書評 バックナンバー一覧
- 『ソーシャル・キャピタル 「きずな」の科学とは何か』
| 文字サイズ: | 大 | 標準 | 小 |
宗教情報PickUp
書評 バックナンバー
2015/04/07
『ソーシャル・キャピタル 「きずな」の科学とは何か』 稲葉陽二ほか著 ミネルヴァ書房
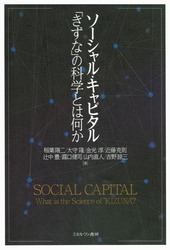 |
| 2014年6月 2800円+税 |
2013年3月15日、日本大学で多分野の研究者らが集まり、社会関係資本研究の20年を振り返るという主旨で報告と討論が行なわれた。本書の内容は、その記録をまとめたもの。20年間という期間は、1995年の阪神・淡路大震災前後から、2011年の東日本大震災を経た今日までを含む。被災地での復興支援ボランティア活動や、地元の生活者たちの相互扶助関係の結び直しなど、いわゆる社会関係(人と人とのつながり)が復興や回復へ向けてのソフトパワーであるという点は、今や多くの人が実感しているところだ。
社会関係資本は「ソーシャル・キャピタル」と訳され、現在ではこちらが一般用語になりつつある。しかし、カタカナ訳語の常として、その意味は収縮と拡散を繰り返す。意味の収縮と拡散の20年を振り返るのは、このキーワードを押さえておくための重要な作業だと言える。本書は、3つの章に分けてこの用語をひも解いている。
第1章「ソーシャル・キャピタルをめぐる議論」ではまず、ソーシャル・キャピタルという概念の検討を行ない、5つのあいまいさを指摘している。第2章「ソーシャル・キャピタルの本質」では、その5つのあいまいさを検討しつつ、この概念の有効性を再検討している。第3章「領域別にみたソーシャル・キャピタル」では、健康、教育、経営、経済、国民性、政治、市民活動など各分野の専門家らがソーシャル・キャピタルを論じている。
本書全体は、ソーシャル・キャピタルについての学問的検討の事例集のような形でまとめられている。副題には、「きずな」とある。それが、社会関係資本やソーシャル・キャピタルと重なりあうものだということは、タイトルにも示唆されているが、どこでどの程度重なるのかは、本書では明言されていない。その探究はむしろ、読者に委ねられている。これは当然だろう。「きずな」という言葉ほど、平易かつ統合的、情緒的でかつ実用的な用語は無く、それゆえに時に思考停止に導くものはないからだ。副題が示すように、読み手の我々が自ら考えることが、「きずな」を科学することだろう。
「きずな」の含意については、本書の「はじめに」の部分で、東日本大震災の時に暴動や社会の混乱や便乗値上げなどがなかった事実をもとに、この時に現れた「きずな」は「お互いさまという意識に基づく規範」(p.vi)ではないかとの指摘がある。つまり、同じ苦境の中で皆が互いにそれを耐え忍び合うこと、また助け合うことが、日本人の「きずな」意識とそれに基づく行動を示しているというわけだ。
ソーシャル・キャピタルは、「心の外部性をともなった信頼・規範・ネットワーク」(p.vi)と定義されている。これら3つは、公共財(一般的信頼、一般的互酬性)、クラブ財(特定化信頼、特定化互酬性)、私的財(個人的ネットワーク)の総称だという(p.vi)。それぞれ、一般社会での規範的行動や活用資源、所属集団や組織に限られた活用資源、個人どうしの結びつきを指す。また、結びつきのパターンという観点からは、このソーシャル・キャピタルは2つに分けられるという。一つ目は同じバックグラウンドを持つ者同士をつなぐ「結束型」、二つ目は異なるバックグラウンドを持つ者同士をつなぐ「橋渡し型」だ。この橋渡し型のなかには、「個人と地方政府間、地方政府と中央政府間など次元の異なる個人と組織の間および組織同士の間の関係を示すリンキング(連接型)なソーシャル・キャピタル」があるという(p.vii)。このような丁寧な整理をもとにして、第3章では教育、健康、経営など諸分野におけるソーシャル・キャピタルが論じられているのである。以下、各章を簡略に概観してみよう。
第1章は、ソーシャル・キャピタルという概念の検討である。まずこの概念が持つ、以下の5つのあいまいさについての指摘がある。1.定義に関するあいまいさ 2.付加価値に関するあいまいさ 3.測定に関するあいまいさ 4.因果関係に関するあいまいさ 5.政策手段としてのあいまいさ である。細かな記述は本文を参照していただくとして、「きずな」の科学としてのソーシャル・キャピタル研究という点から特に注目したいのは、3、4 、そして5のあいまいさについてだ。
ミクロレベルの「個人間のネットワーク」も、マクロレベルの「国民性調査」や「世界価値観調査」なども、等しくソーシャル・キャピタルとして扱うとすれば、測定方法(またその対象や範囲など)を選ぶ際に極めて恣意的にならざるを得ない。これが、3の測定に関するあいまいさの指摘のポイントだ。4の因果関係のあいまいさとは、あるソーシャル・キャピタルが、個人や社会にどう影響したか、逆に個人や社会の動向がソーシャル・キャピタルにどう影響したかという点が、非常に確定しにくいということだ。また、調査・研究者が抱く価値観から離れた客観的な測定方法など無く、ソーシャル・キャピタル研究や獲得されるデータ自体も、その研究・調査者の側に左右されるのではないかという指摘である。
ソーシャル・キャピタルの活用や政策手段の錬成という方向づけは、制度と個人・社会との相互影響関係に配慮しつつも、まずは「気持ちを合わせてみんなで仲良くしようという話になってしまう」(p.11)。その中で政策手段もあいまいなものになり、階級、ジェンダー、マイノリティ、社会的不平等な状況などへの目配りが欠けてしまうというのが、5点目の指摘である。現代日本社会における「つながり」や「きずな」が論じられる際にも、こうした点は欠落しがちで、大状況の中のピックアップできる課題だけをとりあげ、「つながり」や「きずな」の大切さを力説することに終始する傾向がある。逆に言えば、それだけ、ソーシャル・キャピタルは考察に値する事象だということになろう。
第1章の末尾では、ソーシャル・キャピタルには二つの側面があるとの指摘がある。一つは、「世の中をよくしようという、そのために社会的なつながりの潜在能力を高めようという社会運動としての側面」(p.16)。もう一つは、「社会関係資本が持つコミュニティの包括的な分析能力を通して、さまざまな社会で、幸福増進のために学術的な貢献をしている側面」(p.16)だという。コミュニティの包括的理解のための道具として、このソーシャル・キャピタルという概念は学術的に役立つ。これが本章の小括だ。
第2章では、先の5つのあいまいさを検討し、ソーシャル・キャピタルの本質を論じている。ポイントとなるのは、この語の定義に含まれる存在と機能の両面である。OECD(経済協力開発機構)による定義では、ソーシャル・キャピタルは「規範や価値観を共有し、お互いを理解しているような人々で構成されたネットワークで、集団内部または集団間の協力関係の増進に寄与するもの」(p.37)となっているという。
論者の一人、経営学の金光淳は、「ネットワーク」に力点を見出す場合には、社会学においても研究蓄積のある「社会資源論」「ネットワーク理論」「社会構造論」がソーシャル・キャピタル論に先行するものとして参照・評価されるべきだと述べる(pp.51-54)。また、保健学や社会疫学を専門とする近藤克則は、ソーシャル・キャピタルを因果関係の見える調査データに上げるための一例として、コミュニティ内のサロン(集会、会合の場)と自宅との間の「距離」が、ソーシャル・キャピタルを具体的に捉えるための操作変数として使えると述べる(pp.43-48)。近藤の例が興味深いのは、サロンと自宅との距離や、サロンへの参加回数などのデータをもとに、罹病率や健康向上効果を推定できるとしている点だ。人間関係それ自体がソーシャル・キャピタルだという観点に立てば、周囲と没交渉になりがちな高齢者も、まわりの人が訪ねてくるような社会関係資本が豊かなコミュニティでは、生活や健康上の危機を回避できるケースが多くなると言える(p.60)。近藤の調査は、測定方法と因果関係におけるソーシャル・キャピタル概念のあいまいさをクリアしようとする試みとして評価できよう。
第3章は、本書のダイナミクスが盛り込まれた内容になっている。先にもふれたが、健康、教育、経営、経済、国民性、政治、市民活動など各分野の専門家らが、それぞれの立場からソーシャル・キャピタルを論じている。例えば、教育学の露口健司は、「校区におけるソーシャル・キャピタルの視覚化」をテーマに、仙台市内の小学校区のおける家庭・学校・地域社会のソーシャル・キャピタルと学力との相関性を調査した。その結果、「授業適応感」(子どもにとって授業がわかり、子どもが教師に対して信頼感を抱いている状況)が、学力向上において最も大切だということが、データとして分かったという(p.104)。我々の実感としても、「先生と生徒との信頼関係が大切だ」というのは、いわば当たり前のことと考えられよう。しかし、「家庭内での経済状況や生活習慣、通塾、親と学校との信頼関係等が「授業適応感」に行き着き、それが子どもの学習意欲、そして学力に行き着く」(p.104)という経路を、調査データとともに明らかにしたことは重要である。これは、ソーシャル・キャピタル論の展開・応用の一つとして興味深い。
また、経済学の大守隆は、経済学の観点からソーシャル・キャピタルを論じている。大守はソーシャル・キャピタルの「資本としての特性」に言及し、物的資本と異なり「社会関係資本の一つの大きな特徴は、使い続けると強化されることがある」(p.160)という点を指摘している。物的資本は、使っても傷み、時間がたっても傷み、「減価償却」を考えなくてはならないが、「一緒に何かプロジェクトをやると、人々の間の信頼関係が醸成されて次のプロジェクトは多分よりやりやすくなる」(p.161)と。一方で大守は、こうしたソーシャル・キャピタルの負の側面も指摘する。一例として挙げるのは、KY(空気を読む)という現代日本社会の風潮だ。「KYであっても筋を通す人たちが敬遠されるような社会的雰囲気がある」(p.171)と。太平洋戦争の開戦に至る経緯、バブル崩壊後の不良債券処理の先送り、津波対策の遅れなども、ソーシャル・キャピタルとして培ってきた日本の社会関係とそれが醸成する心性に起因しているというわけだ。このあたりは、日常では「しがらみ」や「面子」といった言葉で意識されているものだが、これがソーシャル・キャピタル論とどのように繋がっているのかという点は、「きずな」を科学することと同様に、我々が日常の中で省察していくべきことだろう。
市民社会論からのソーシャル・キャピタルの検討も、興味深い。公共政策学の山内直人は、ソーシャル・キャピタルと市民活動と幸福度の3つの概念の関係について述べている。大阪商業大学のJGSS(Japanese General Social Survey)研究センターのデータを参照しながら山内が指摘するのは、寄付・ボランティア参加の有無によって個々人の幸福度に差異がみられるという点だ。「他人のために何かをしたということ自体が、その人の幸福度を高めるという関係がある」(p.226)という。また、東日本大震災後の人々の意識や行動の変化を調査した結果、寄付は「絆」や「つながり」の意識を高め、ボランティアは「当事者意識」を高めるという結果が出たという。そして「寄付もボランティアもしたという人は、「絆やつながり」とともに当事者意識が非常に高まっているということ」(p.232)が分かるという。山内は「絆やつながり」をソーシャル・キャピタルに関係するものとして仮説を立てて結果を分析している。結論を端的にまとめれば、寄付やボランティア活動は主観的幸福度とプラスの相互関係がありそうだということである(p.233-235)。政策として、寄付やボランティアを促進すれば、参加・行為者らの幸福度も向上する可能性があるということである。こうした調査結果によって、ソーシャル・キャピタル論のすそ野もまた広がっていくと思われる。
以上、広範な本書の内容の一部を紹介してきた。存在としてのソーシャル・キャピタルを絶対化せず、また、つながりを促す機能を読み込んだだけのソーシャル・キャピタル論に終始せずに、この新しい概念を深堀りしていくには、本書で試みられているように多くの領域での調査・検討を擦り合わせていく努力が必要である。その際には、1章で指摘されているように、これを存在(実体)としてみるか、機能(はたらき)としてみるかという両点をしっかり押さえることが重要だろう。
繰り返しになるが、本書の副題は<「きずな」の科学とは何か>であった。絆は、2011年のユーキャン新語・流行語大賞のトップ10にノミネートされた言葉としても記憶に新しい。Webサイトの解説文には、次のようにある。
未曾有の大災害である東日本大震災は、人々に「絆」の大切さを再認識さ
せた。復興に際しての日本全体の支援・協力の意識の高まりだけでなく、地
域社会でのつながりを大切にしようとする動きや、結婚に至るカップルの増
加などの現象がみられた。
(http://singo.jiyu.co.jp/nendo/2011.html)
ここでは、復興の支援と協力、地域社会でのつながりの見直しが、絆という言葉が浮上した要因として挙げられている。また同箇所には流行語の「受賞者」も明記されているが、絆の受賞者のところには、「なし 今活動しているボランティアを含め日本国民、そして海外から日本を応援くださったすべてのみなさま」とある。ボランティア参加者、日本国民、海外からの応援者すべて、この「絆」という言葉の下でまとめられている。これを読み、「絆」を科学するということは、じつは壮大なプロジェクトであり、ミクロとマクロが縦横に交差する現場に分け入っていくことだということに思い至る。
哲学者の中島義道は、『反<絆>論』(ちくま新書 2014)の中で、「繊細な精神」をもちつつ、表層的にオールジャパン化する今日の「絆」を批判している。中島は、「絆」に馴染まない人間がいることへの配慮や想像力が、この日本社会に欠けていることを憂慮する。そこに目配りをするために、(哲学者としては)「繊細な精神」を持たねばと。パスカルに由来するこの「繊細な精神」でもって「絆」を考えていくことと「絆」を科学することは、果たして対立するのか、しないのか。絆という言葉をソーシャル・キャピタルという用語に接続させる議論には、本書がカバーする広範な内容を越えてなお相当の広がりがある。
(宗教情報センター研究員 佐藤壮広)
