- トップ
- 宗教情報PickUp
- 書評
- 書評 バックナンバー一覧
- 『宗教と現代がわかる本 2014』 平凡社
| 文字サイズ: | 大 | 標準 | 小 |
宗教情報PickUp
書評 バックナンバー
2014/05/14
『宗教と現代がわかる本』 渡邊直樹 責任編集 平凡社
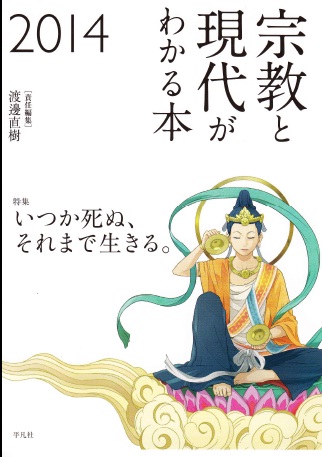 |
| 2014年3月 1600円+税 |
本書は、珍しい年次刊行物である。その理由は、宗教現象の現代的な諸相を一般読者にも分かりやすく紹介する内容をその特徴としているからだ。宗教についての学術的な研究報告・論文は、『宗教研究』(日本宗教学会)や『宗教と社会』(「宗教と社会」学会)などで読むことができる。また、Web上で購読できる公益財団法人国際宗教研究所編『現代宗教』でも、宗教の諸動向についての専門家らの分析にふれることがきる。さらにここ数年、一般誌でもキリスト教、神道、仏教の紹介・解説で特集を組み、聖地やパワースポット巡りの記事を載せるものも多くなってきた。しかし、宗教についての様々な論点を網羅的に知ることのできるという点で、本書はやはり独自の意義を持っていると言える。
責任編集の渡邊直樹は、2007年の創刊のことばで、次のように語っている。「日本では宗教について学ぶ機会を持たない人がほとんどのため、これらの問題(引用者注:聖地巡礼ブーム、生命操作と倫理、国会議員の靖国参拝問題、皇位継承問題、教育基本法の改正など)に直面しても、きちんとした理解も説明も議論もできないままでいるのではないでしょうか」(『宗教と現代がわかる2007』刊行にあたって)。7年を経た現在も、状況はほぼ変わらない。宗教についての知識を身につけ、その意味を多角的に考える機会は、一部の宗門系およびミッション系の学校(小学校から大学まで)での授業を除き、まだまだ少ないのが実情だ。
ところで、ここ20年ほどの間に限ってみても、1995年のオウム真理教による地下鉄サリン事件(=宗教が引き起こす暴力)、2001年9月の同時多発テロ事件(=原理主義とテロ)、2005年3月の阪神・淡路大震災(災害と慰霊、ボランティアと宗教)、2011年3月の東日本大震災(科学時代における宗教、死者の弔いと地域復興)等々、宗教という観点からその深層を捉えるべき大きな事象がたくさんある。こうした時代・社会状況の中だからこそ、本書の意義もまた大きくなるのである。この点を確認した上で、2014年版を見ていこう。
本書で組まれた特集は、「いつか死ぬ、それまで生きる。」だ。主旨には「「生者」は「死者」と無関係に生きているのではない、という感覚を多くの人が持つようになっています」(p.25)とある。多くの日本人が被災して犠牲となった死者とどう向き合うか、弔うかという、大震災を通して多くの人々が共有する経験が、この言葉の背景にある。つまり、現今の日本人の精神状況を再考することが課題だという意識があっての特集なのである。各論を読んでみよう。
在宅緩和ケア医師・萬田緑平は論考「癌患者を中心とする在宅緩和ケア」の中で、緩和ケアは「看取り屋」ではなく「生き抜き屋」であり、「自宅で最後までめいっぱい生きることを支援する」仕事(p.33)だと述べている。やがて訪れるのは死であっても、それを家族や支援者に囲まれて迎えることが生の充実なのだという力強いメッセージが、ここには込められている。続いて、宗教・宗派の垣根を越えて被災者のケアを行う「臨床宗教師」の構想と実際についての、東北大学大学院准教授・高橋原によるレポートがある。被災者と向き合う際、「相手の苦悩を慎重に受け止めるスピリチュアルケアのセンスが問われている」(p.49)という指摘は、ふだんの生活の中で死別の悲しみを抱えた人に向き合う姿勢を示唆するものとして興味深い。特に、「スピリチュアル」のあとに「センス」という言葉が出てきているところは、今後のこの論点が拓かれていく方向としても重要だと思われる。続く論考「憶えてるよ、忘れないよ」で、評論家・東雅夫は、東日本大震災の被災者らが死者との邂逅を語る「震災怪談」なるものに、遺された人たちの精神のかたちを読み取っている。
特集にはまた、二つの対談が収められている。ひとつは、1973年に日本で初めて「ホスピス・プログラム」を立ち上げた柏木哲夫医師と宗教学者・島薗進との対談「ホスピス、死生学、ユーモアの効用、上手な死に方」。もうひとつは、インド哲学者・下田正弘と批評家・若松英輔が、日本で初めて『コーラン』の原典訳をした比較思想家・井筒俊彦を手がかりとして「死者」「言葉と沈黙」「真理」について語った対談だ。後者の対談の中で若松は、“「死生学」への違和感”を語っている。曰く「「死生学」という述語にはどこか死を了解している感じがある。(中略)生者は死を知らない。そんな生者が「死生学」を論じることができるのか」(p.109)と。一方でまた、「「死生学」は必要です。しかし、それは死を概念として考える者にではなく、迫りくる死を生きる者に必要なのだと思うのです」(p.109)と述べ、生きるということにわれわれの言葉がいかに直に関わっているかという認識が、もっともっと必要だと強調している。そして、それを実践したのが井筒俊彦だという。この対談は、言葉と「生と死」の関係、死生学と死、宗教学と宗教のあり方を簡明に、しかも深く語っており、非常に読みごたえがある。
以上の特集のページのあと本書は、テーマ、インタビュー、レポート、対談と続く。テーマの部分では、2013年が伊勢神宮の式年遷宮にあたったこともあり、斉藤英喜・佛教大学教授の「変革する聖地、伊勢神宮」という論考も収められている。パワースポットブームも相まって参拝者が1000万人を超えた伊勢神宮だが、神宮司庁や神社本庁では、パワースポット化することへの懸念が大きいという。しかし、国内外の研究者によるシンポジウムでは、「おかげ参り」に代表されるように、「流動化する、ダイナミックな伊勢神宮の歴史」が焦点だったと斉藤は指摘する。そして「そもそも中世における伊勢神宮こそが「パワースポット」であったことは、歴史に分け入れば明らかであろう」(p.133)と述べる。「パワースポット」の意味を歴史から抽出する試みとして、この論考も興味深い。
インタビューでは、作家・石井光太が物語の力について語っている。東日本大震災直後に取材に入り、『遺体 震災、津波の果てに』(新潮社、2011)を書いた石井は、現場を歩く中で聴き取った個人の物語に発現するものを「小さな神様」と表現する。取材者として相手の声を聴き「個人の文脈を理解した上でないと「小さな神様」を見極めることはできないんです」(p.144)と。この「小さな神様」は、語り手の存在を根拠、あるいは語り手を支える人間およびそれを超えたつながりのようなものだ。石井は、そうしたものを取材現場で感受するからこそ、作品が書けるという。このあたりは、他者と向き合い、声を聴き、それを書いていくという作業が、ある種の宗教性を帯びた作業に他ならないということを告白したものとしても興味深い。
本書の後半部には、87ページにおよぶ現代宗教関連データ(国内外ニュース、用語・新語解説、ブックレビュー、映画ガイド、展覧会レビューなど)が付されている。この構成は、創刊以来ほぼ同じだ。しかし、毎年同じボリュームで「宗教関連情報」が更新されていると考えるならば、8号にわたり蓄積されてきたデータは、宗教と現代を読みとくための必須の情報だと言えよう。
以上のように、本書は内容も量も非常に充実している。但し、繰り返しになるが、「分かりやすさ」や「答え」を提供するのが本書の意図ではない。あらためて2007年版の「刊行のことば」を見てみよう。
ただし、どのテーマもすぐに答えが出るような簡単な問題ではありません。ここには、「ひとことで言えば」といった自信満々な 断言や、耳に心地よいだけの気の利いたフレーズの「回答」はありません。現代が抱える問題は、単純に「正義と悪」で割り切 れるようなものではないからです。(『宗教と現代がわかる2007』刊行にあたって)
本書が取りあげるのは「問いとしてのトピック」だ、ということになろう。「すぐれた問いは答えを含む」と言われるように、『宗教と現代がわかる本』は、現代において宗教を問い続ける。そして読者に宗教という課題に向き合ういくつものヒントと構えを示してくれる、優れたテーマ書籍だと言える。
(宗教情報センター研究員 佐藤壮広)
