- トップ
- 宗教情報PickUp
- 書評
- 書評 バックナンバー一覧
- 『「いのちの思想」を掘り起こす――生命倫理の再生に向けて』 安藤泰至(編)
| 文字サイズ: | 大 | 標準 | 小 |
宗教情報PickUp
書評 バックナンバー
2011/11/14
『「いのちの思想」を掘り起こす――生命倫理の再生に向けて』
安藤泰至(編) 岩波書店 2011年
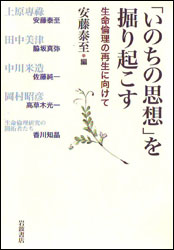 |
病院での手術や治療の際に、切除した部位を標本として実験に供することの承諾、また新薬の治験を受けることの承諾が求められることがある。医師の説明を受け、基本的には、医師を信じて、(拒否も選択できるけれどもたいていは)これらを唯々諾々と署名することが多い。説明を受けての判断という流れにのって、私たちは「生命倫理」に直面する現場に置かれるわけである。 本書は、個性的な人物たちの生と仕事をていねいに追いながら、現代日本における「いのち」のありかたについて問い直す好著である。扱われるのは、歴史学者上原專祿、ウーマンリブの発言者のひとり田中美津、医学への問いを一般市民へと広げるのに貢献した中川米造、戦争カメラマンとしての経験から生命倫理の代弁者となった岡村昭彦の4人におのおの一章が割り当てられ、そして5章で、加藤尚武、森岡正博、木村利人、中村桂子、米本昌平ら、日本の生命倫理史における重要人物がそれぞれ果たした役割が俯瞰される。 |
|
生命倫理の専門家ではない読者にとって、生命倫理とは、臓器移植や遺伝子治療などの「問題」をどう判断すべきかに一定の答えを出し、それらの是非について判断を下し、そしてその結果、当事者みながより幸福になり、また当事者全員の意思が望ましい形で反映される落としどころを見出す学問、といったところであろう。しかし編者の安藤は、「臓器移植や遺伝子治療など」に関わる諸手続きが生命倫理学によって制度化された結果、生命倫理は、(それらについて深く考えさせるどころか、逆に)深く考えずに、それらを早急に処理するための道具になってしまった、と慨嘆する。そして、本書は全体として、人間のいのちのありかた、生のありかたについて深くこだわり悩んだ人物に沿って、私たちの生をともに考えるものとなっている。 各章の内容を簡単にまとめておこう。 第1章は、妻・利子の死をめぐる上原專祿の苦悩が、医療と宗教とを同時に問う思想へと結実した過程を追う。上原の著作は、医師たちの治療や診断の冷酷さに加え、人の生死の苦難に寄り添えない宗教者の問題性を問うものであるという。 第2章は、同時代の犯罪者や受難者に対して、「永田洋子はあたしだ」「戦災孤児はあたし」「永山則夫はあたしだ」と言う田中美津を採り上げる。こうした言明は、彼らの個別の体験の理解や共感ではけっしてなく、私に徹底的にこだわるという田中の姿勢(構え)の現れであると著者は主張する(73頁)。共感でなければ何か? 田中は自他の生に起こるアンビヴァレンツにゆらがされる状態(「とり乱し」)であるという。この「とり乱し」は、人間の個々の生がかけがえのないものでありながら同時にたまたまそうなったものであるという現実を再考させるキーワードである。 第3章は、現代医学について、またその望ましいありかたについて「医学概論」で市民へと問いかけ続けた中川米造論。戦時中の「兵器としての医学」に触れ、また医師免許を持たないで診療をさせられた経験から、医学とは何のためかと中川は問う。中川が期待するのは、生態学的な「社会の医学」、社会レベルで健康や不健康を問題にし、市民や患者や弱者が主体となり、彼らの立場に立つ医学である(130-140頁)。 ヴェトナム戦争写真家として名を馳せた岡村昭彦が、木村利人との友誼を介して、日本にまいた生命倫理の種がどのようなものであったかを述べるのが第4章。『ライフ』誌のカメラマンとして時代を追う岡村と重なる、DNAの二重らせん構造の発見や、ヴェトナム戦争における枯れ葉剤使用などの出来事。両者とも、科学技術が医学の可能性を広げるとともにいのちへの侵襲ももたらす危険を浮き彫りにし、岡村や木村をバイオエシックスという新しい学問(とその導入)へと駆り立てた。 第5章は、日本における生命倫理学史のこころみであり、統合的なライフサイエンスや、市民的な異議申し立てなど、さまざまな方向性を孕んでいたことを俯瞰する。 本書の読者は、とりあげられた人物の語りや挿話のおもしろさをまず楽しむであろう。生命倫理学会の前会長でもある木村利人が、「しあわせなら手をたたこう」の作詞者でもあることをご存じだっただろうか……。同時に読者は、人物が問いかけた課題にも直面させられる。評者がもっとも好感を覚えたのは、中川米造からのさまざまな市民への語りかけ(139-140頁)であり、また田中美津が人生の「巾」とリブ運動の限界や、「とり乱し」というキーワードで表現した、人生における多様なアンビヴァレンツとの直面であった。一方、上原や田中の思想がいのちについてさまざまな問いを投げかけるものではあるものの、彼らが提示するアンビヴァレンツに対しては、多くの人がどのように抱えていけるのか、その方策はどうなっていくのだろうと、それぞれの著者たちに問うてみたい。アンビヴァレンツを抱え込むのは、決して軽いことではないからである。そしてその重さは、生命倫理がどうしても一つの手続き体系と化してしまう傾向の一因であるからである。評者は、中川米造が語りかけるという形、中川を囲む市民の共同体の中に、一つのヒントがあるように考えている。
(葛西賢太 研究員) |
|
