コスモロジーと出会うよろこび【編集部から】
本連載エッセイでは、人類共通の記憶の宝庫ともいうべきコスモロジー(=世界観・宇宙観)の豊かさを武澤秀一先生が探究します。
建築家である先生は、ご著書『空海 塔のコスモロジー』『マンダラの謎を解く』『神社霊場ルーツをめぐる』に見られるように、3次元の存在である建築を歴史・宗教・文化の位相のなかに捉え、塔やマンダラや神社霊場が聖なる力を帯びていく様相を明らかにされてきました。そして今年3月に刊行された新著『伊勢神宮の謎を解く』は、とくに日本の特性を浮かび上がらせていて注目されます。本連載エッセイにあわせて、ぜひごらんください。これからの連載でも、日本列島において育まれてきたわたしたちのこころの特性に、さまざまな場面で気づかせてくれることでしょう。
さあ、コスモロジーに出会う旅に出発することにいたしましょう。わたしたちが無意識の底に置き去りにしてきた大切なものに、今、再び出会うために——。
建築家 武澤秀一の連載エッセイ 時空を超えて コスモロジーと出会う
第18回 北の仏国土 (上)
|
1
2011年6月26日、東北地方の中心に位置する「平泉(ひらいずみ)」が世界遺産に登録され、被災地の復旧・復興にむけてのシンボルとして、大きな灯となりました。登録された文化遺産の内容は、以下のものです。
おそらく、現地を訪れたひとの多くが感じるのは、地上にのこっている当時のものが意外と少ないことです。「平泉」が世界遺産に登録されるに際し、一度は棚上げされ、予想以上に時間を要したのもこの点にあったといえましょう。つまり、多くの遺産は消失したか、あるいはその痕跡が地中に眠っているかというのが現状です。 |
〈奥州藤原氏三代、滅亡時の報告書〉
平安後期の12世紀に平泉を拠点とする、清衡(きよひら)、基衡(もとひら)、秀衡(ひでひら)とつづいた奥州藤原氏三代、最後の泰衡(やすひら)を含めると四代の栄枯盛衰の歴史がありました。その90~100年を振り返りますと、平泉を中心として東北の地全体を仏国土(=浄土)にしようと構想し、これを実現しようとしたきわめてユニークな試みであったということができます。 |
〈仏国土の中心に〉緊迫した状況下、頼朝にたいして提出された文書ですので、非常に信頼性の高いものです。8項目からなりますが、その最初に中尊寺が挙げられています。 一 関山(かんざん)中尊寺の事 関山とは中尊寺のある山で、標高150メートルほどの丘陵。中尊寺の山号でもあります【写真H-4】【写真H-5】。
当時、堂塔の数は40余り、僧の住む僧房は300余りもあったといいます。
初代清衡がこの地域を統治するに当たって最初に中尊寺を開いたことを、さきの「寺塔己下注文」は述べていますが、注目すべきは、そのつぎの箇所です。(さきの「寺塔己下注文」引用箇所を再度参照してください) |
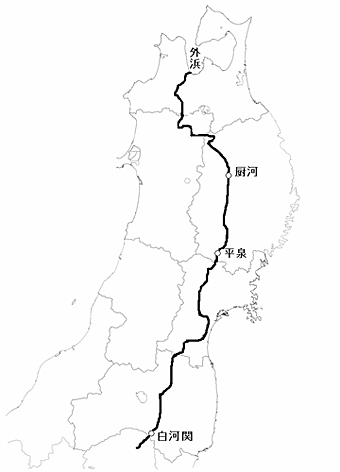
【図H-1】:奥大道略図。ちょうど真ん中の地点に平泉が位置する
|
解説をくわえますと、当時、白河の関を越えると蝦夷の地といわれていました。栃木と福島の県境に近い白河の関は、蝦夷の地の、いわば南限です。そして外浜(そとのはま)は往時の呼称で、現在は外ケ浜(そとがはま)ですが、そこは青森県は津軽半島の陸奥湾側。蝦夷の地の南限の白河の関から平泉をとおって北限の外ケ浜まで至る道は奥大道(おくだいどう)と呼ばれます【図H-1】 |
〈戦乱の世の果てに〉
じつは、平泉を語るには、東北地方に勃発した前九年の役(ぜんくねんのえき。1051年~1062年)と後三年の役(ごさんねんのえき。1083年~1087年)という、壮絶きわまる二つの内戦を忘れるわけにはいきません。 |
〈中尊寺の世界観〉1126年、中尊寺が建立された際に清衡によって読み上げられたという「中尊寺供養願文(ちゅうそんじくようがんもん)」に、耳を傾けてみましょう(この時、清衡数え71歳)。 鐘の音は世界の隅々にまで響きわたり、分け隔てなく平等に、だれからも苦しみを取り去り、だれにも安らぎをあたえてくれる。朝廷から派遣されてきた官軍からも、蝦夷とさげすまれてきた土地の人びとからも、古来、多くの死者を出してきた。また動物、鳥、魚介など無数の生き物が犠牲になっている。浄められた魂はみなあの世に往ったが、骨は朽ち、この世の塵となっている。大地に響きわたる鐘の声よ、鳴るたびごとに、さまよえる魂を浄土に導いてほしい。(拙訳)
平和をもとめて、浄土への鎮魂を願う、まさに仏教の精華といえることばではないでしょうか。 |
 |
武澤 秀一(たけざわしゅういち) 1947年群馬県生まれ。建築家/博士(工学・東京大学)。東京大学工学部建築学科卒業。同大学院を中退し、同大学助手をへて建築家として独立。設計活動の傍ら、東京大学、法政大学などで設計教育指導に当たった。20代、30代はヨーロッパ志向がつよかったが、40代に入りインド行脚をはじめる。50代以降は中国、韓国および日本列島各地のフィールドワークを重ねている。著者に、『マンダラの謎を解く』(講談社現代新書)、『空海 塔のコスモロジー』(春秋社)、『法隆寺の謎を解く』(ちくま新書)、『神社霊場 ルーツをめぐる』(光文社新書)、『伊勢神宮の謎を解く——アマテラスと天皇の「発明」』(ちくま新書)などがある。 |







